「花」という単語や花の種類が含まれたことわざは数多くあります。花を含むことわざの意味は非常にさまざまで、日常的に使える言葉や褒め言葉として使える洒落たことわざも。この記事では、花に関することわざを24個紹介しますのでぜひご覧ください。
日常でも使える花のことわざ6選
- 言わぬが花
- 言わない方がかえって良いことの例え。知っていてもあえて隠しておくべきシーンや、余計なことを言わないよう慎むときに使います。なお、逆の立場のことわざとして「知らぬが仏(知らない方が良いこともあることの例え)」があります。
- 花より団子
- 「花を見るよりも団子を食べる方が良い」という意味であり、風流を特に気にしないことや、見た目・品格よりも実利をとることの例えとして使われます。お花見シーズンになるとよく聞くことわざですので、花を含むことわざの中でも知名度がある言葉ではないでしょうか。
- 美しい花(バラ)にはトゲがある
- 美しいものにも危険な一面があることを示すことわざです。上手い話には穴があるといった意味で使われたり、綺麗な女性を花に例えてこのことわざが使われたりします。なお、語源となったのは英語のことわざ「There’s no rose without a thorn(トゲのないバラはない)」です。
- 埋もれ木に花が咲く
- 長い間逆境や不運な状況にいた人に幸運が訪れるという意味です。また、しばらく世間から忘れられていた人が再び脚光を浴びる例えとしても使われます。なお、埋もれ木とは地殻変動や火山活動などにより樹木の幹が地中に埋もれ、長い年月をかけて炭化が進んだ状態を指しています。
- 隣の花は赤い
- 「同じ花なのに隣の家の方が綺麗な赤に見える」という意味で、他者のものは自分のものより良く見えてしまう例えです。「隣の芝生は青い」と同じ意味のことわざです。人は人、自分は自分だと考える大切さを説いているようにも思えます。
- 花に嵐
- 良い物事には邪魔が入りやすいことの例え。せっかく綺麗な花が咲いたのに、嵐で散ってしまう様子からこのことわざが作られました。似た意味のことわざとして「月に叢雲(むらくも)、花に風」があります。叢雲は群がり集まった雲のことで、中秋の名月にかかる邪魔な雲を表しています。
褒め言葉などいい意味で使われる花のことわざ6選

- 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花
- 立ち姿・座り姿・歩き姿どれをとっても花のように艶やかで可憐である様子を表しています。花の存在はよく女性に例えられますが、このことわざも美人の形容を表したことわざです。芍薬・牡丹・百合はどれも大輪の花を咲かせるため、目を引き付ける美しい花です。
- 花のかんばせ
- まるで花のように美しい顔の例え。かんばせとは、顔つきや容貌という意味です。このことわざは、明治時代に創作された落語の怪談ばなし「牡丹灯籠」の中で「花のかんばせ月の眉女子にして見まほしき優男」という一節にも登場します。
- 錦上(きんじょう)、花を添える
- 「良いこと・めでたいことが重なる」という意味のことわざです。錦(にしき)とは2色以上の色糸や金銀糸から作った高級な絹織物です。美しい錦の上に、花を添えてさらに美しくすることからこのことわざが生まれました。
- 梅にウグイス
- 調和しているものや仲睦まじいことの例えとして使われます。淡い緑色のウグイスが、梅の木にとまっている姿はとても絵になります。また、このことわざは時候の挨拶にもなり、「梅鴬の候(ばいおうのこう)」が2月に用いられます。
- 解語(かいご)の花
- 美人を意味することわざです。解語とは言葉を解するということであり、このことわざは「言葉を理解する花」を表しています。一説によると唐の第9代皇帝である玄宗が、楊貴妃の美しさを表す際に「解語の花」と言ったとされています。
- 生る木は花から違う
- 優れた人物は、はじめから凡人とはどことなく違うことの例えです。「実のよく生る木は、花が咲いたときから違う」ということを表しています。似たことわざとして「栴檀は双葉より芳し(せんだんはふたばよりかんばし)」があり、大成する人は幼少期から優れているという意味で使われます。
風流を感じるおもしろい花のことわざ6選
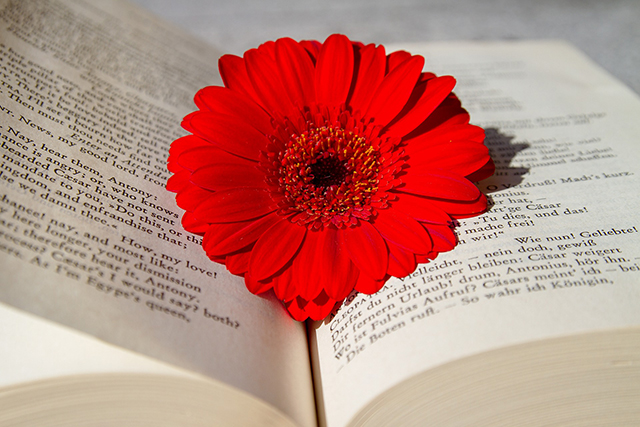
- 花咲く春にあう
- 長い間不遇の環境にいた人がようやく認められ、世の中に注目されることを意味することわざです。冬の間咲くことのできなかった花が、時の流れで春にめぐりあい開花することを表しています。生前は評価されなかった芸術家ゴッホが思い出されることわざですね。
- 柳は緑花は紅
- 人工的ではなく、自然があるがままの美しさを意味することわざです。春になると柳が緑に、花は紅に色付くのが自然の理にかなっていることを表しています。また「ものにはそれぞれの個性が備わっている」という意味として使われることもあります。
- 綺麗な花は山に咲く
- 本当に良いものや価値のあるものは、人々に気付かれにくい場所にあることの例え。庭に咲いている花は人目につきやすいですが、山に咲く花の美しさは山へ行った人だけが知っています。「大切なものは見えないところに隠れているだけ」を表しており、心に響く名ことわざですね。
- 死んで花実が咲くものか
- 生きてさえいれば良いこともめぐってくるが、死んでしまっては何にもならないことを意味しています。花実は人生における成功や良いことの例えです。失敗に落ち込んでいる人や、生きる気力を失くしている人を励ますときなどに使えることわざです。
- 薪(たきぎ)に花
- 外見は乱暴で荒々しい印象でも、内には優しさや風情をたたえていることを表しています。薪を割る山人が、積んだ薪に野の花を添える姿がイメージとなっています。外見と内面は必ずしも比例しないことの例えとしても使えることわざですね。
- 遠きは花の香り
- 遠くにあるものは良く感じられ、近くにあるものほどつまらなく感じられることの意。遠くにありよく知らないときは評価が良いのに、いざ近くで体験してみると低く評価してしまうことが誰しもあるのではないでしょうか。似た意味のことわざとして「聞くと見るとは大違い」などがあります。
特定の花の種類を含むことわざ6選

- 泥中の蓮(でいちゅうのはちす)
- 汚れや煩悩にまみれた俗世においても、清らかさを保つことを表しています。蓮(ハス、ハチス)は泥の中でも綺麗な咲き姿を見せることから、このことわざが生まれました。なお、蓮は仏教では極楽浄土に咲く花とも言われています。
- ハコベの花がとじると雨になる
- 七草のひとつとしても知られるナデシコ科のハコベ。ハコベは空気中の水分が多くなると花をとじる性質をもっています。そのため、ハコベの花がとじたときは雨が降りやすいという天気予報のことわざが生まれました。
- いずれ菖蒲(アヤメ)か杜若(カキツバタ)
- 「どちらも美しく区別ができない」「どちらも優れており甲乙つけがたい」という意味のことわざです。アヤメとカキツバタは姿が非常に似ていますが、よく見ると花の大きさや模様が異なります。また、開花場所もアヤメは乾燥した土地に咲き、カキツバタは水辺に咲くといった違いがあります。
アヤメやカキツバタについては以下の記事も紹介していますので、良ければご覧ください。
- 朝顔の花一時
- 物事の盛りが一瞬で終わることや、はかない様子を表した例えです。朝顔は朝に開花しても昼前にはしぼんでしまいます。その訳は、暑さと乾燥により花びらの水分が蒸発してしまうためです。
- やはり野におけ蓮華草
- 「自然のままが一番」「適した環境に置いておくのが良い」という意味を表しています。蓮華草はハスによく似た姿をしており、ピンク色の鮮やかな花を咲かせます。持ち帰るよりも野原で見る蓮華草が美しいという意味から、このことわざがつけられました。
- 世の中は三日見ぬ間に桜かな
- 世の中は移り変わりが激しいことを示しています。桜は開花したら短期間で散ってしまいます。3日も経てば桜は散ってしまうという様子を、世の中の流れに例えたことわざです。このことわざは江戸時代中期にできたそうですが、情報社会の現在は当時よりさらに早く時代が移り変わっていることでしょう。
花のことわざまとめ
この記事では花に関することわざを計24個ご紹介しました。褒め言葉や良い意味で使われることわざなら、日常で聞くことがあるかもしれません。「花より団子」や「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」は花を使ったことわざの中でも特に有名ですね。ことわざは日本語のおもしろさや美しさを知る良い機会となるでしょう。







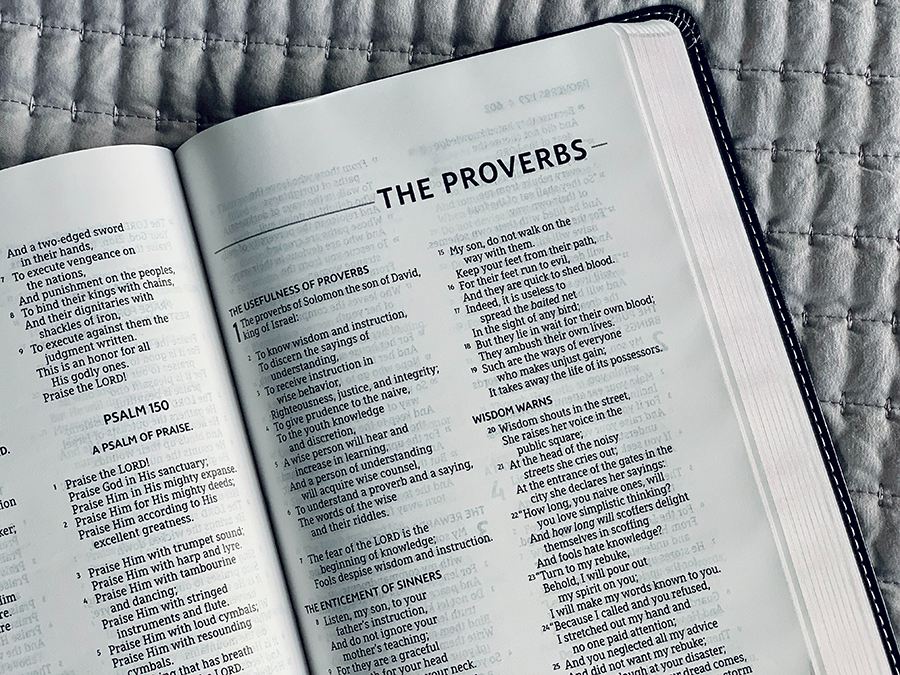


























この記事へのコメントはありません。